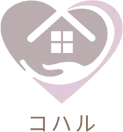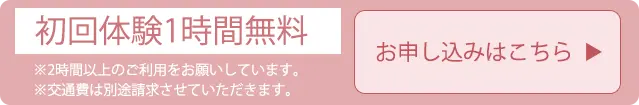こんにちは プライベートナーシングコハルです。
今日は、介護・医療が必要になったとき、どんな手続きを踏めばよいかをお伝えしたいと思います。
転倒してしまって急に寝たきりになってしまった。
病気になってしまい、寝て過ごすことが多くなった。
こんな時、どうすれば分からず不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、介護・医療保険サービスとはどのようなものなのか。
どんなメリットがあるのか
そして、利用するまでの一連の流れやポイントを分かりやすく解説します
どうすればいいかとご不安になられているあなたやご家族様のお役にたてると幸いです。
介護保険制度とは
・家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えることを目的に、2000年に創設されたものが介護保険制度です。
・介護離職ゼロを目指して
介護を理由として離職する方が毎年約10 万人いると言われています。政府は、介護サービスの確保を図るとともに、働く環境の改善や、家族への支援を行っています
介護保険制度で受けられるサービス

- 自宅で受けられるサービス
ヘルパーや看護師、リハビリ、薬剤師が自宅にきてくれるサービスです - 通って受けられるサービス
ディケア・ディサービス、小規模多機能型住宅居宅介護など、自宅から通って受けられる半日、一日、24時間のサービスです - 生活環境を整えるためのサービス
福祉用具貸与や購入費補助、手すりや段差解消などのリフォーム費の補助 - 施設サービス
グループホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設などがあります - 計画をつくるためのサービス
心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成したり、ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行います
介護保険サービス利用までの大まかな流れ
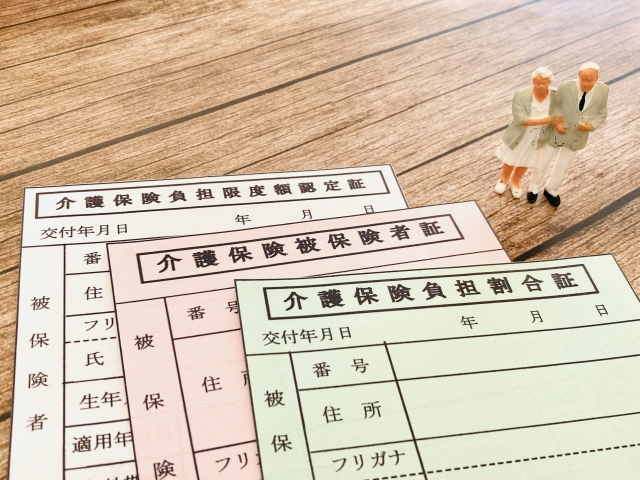
- 要介護認定の申請
- 介護サービスを利用するには、まず「要介護認定」の申請が必要です。
- 申請は本人または家族などが、市区町村の窓口に必要書類を提出して行います。
- 申請に必要なもの
- 要介護(要支援)認定申請書
- 介護保険被保険者証(40~64歳の方は健康保険証)
- マイナンバーが確認できるもの
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 代理申請の場合は印鑑も必要です。
- 訪問調査の実施
- 市区町村の担当者やケアマネジャーが自宅を訪問し、本人や家族に聞き取り調査を行います。
- 身体機能や生活機能、認知機能などについて細かくチェックされます。
- 入院中の場合は、ベッドまで調査員が来てくれます。
- 主治医の意見書作成
- かかりつけ医がいる場合は主治医に意見書を依頼します。
- いない場合は市区町村指定の医療機関で診断を受けます。
- 一次判定・二次判定(審査会)
- 訪問調査の結果や主治医意見書をもとに、コンピュータ判定(一次判定)と専門家による審査会(二次判定)が行われます。
- 訪問調査の結果や主治医意見書をもとに、コンピュータ判定(一次判定)と専門家による審査会(二次判定)が行われます。
- 認定結果の通知
- 申請から原則30日以内に、要支援1・2、要介護1~5のいずれかに認定されます。
- 結果は郵送で届きます。
- ケアプランの作成
- 要介護認定を受けたら、ケアマネジャーと相談してケアプラン(介護サービスの利用計画)を作成します。
- 要支援の場合は中学校区に約1つある、地域包括支援センターが対応します。
- サービス開始
- ケアプランに基づき、実際に介護サービスの利用が始まります。
要介護認定の基準と目安
- 身体機能や日常生活動作、認知機能、精神・行動障害、社会生活の適応力などが調査されます。
- 認定区分は「要支援1・2」「要介護1~5」に分かれ、状態に応じて利用できるサービスや自己負担額が異なります。
申請時のポイントと注意点
- 申請から認定まで1か月ほどかかるため、早めの準備が大切です。
- 認定結果に納得できない場合は、不服申し立てや再申請が可能です。
- 市区町村ごとに運用や窓口名称が異なる場合があるので、事前に自治体のホームページ等で確認しましょう。
訪問診療の対象

では、どんな状態だったら、自宅に医師が来てくれる訪問診療が受けられるのでしょうか。
結論から言うと、
自宅療養中で、通院が困難な方
となります。
具体的には、
・病気、障がいによって歩行が困難で通院が困難な方
・自宅での看取りを希望されている方
などです。
ご自身の状況が対象になるかどうかは、かかりつけ医や担当ケアマネジャー、病院の相談員に相談してみてください。
利用が決まれば、診療情報提供書、医療保険証、介護保険証、印鑑などを用意して契約手続きを行い、定期的な訪問診療が始まります。
医療費の支払い・公的制度の利用

- 医療費の自己負担が高額になった場合、「高額療養費制度」を利用できます。加入している健康保険組合や市区町村で申請書を入手し、必要書類とともに提出します。
- やむを得ず医療費を全額自己負担した場合も、後から療養費として払い戻しを受けられる場合があります1。
まとめ
介護・医療が必要になったとき、介護保険サービスや医療サービス、公的制度を上手に活用することで、経済的・精神的な負担を軽減できます。かかりつけ医や、ケアマネジャー、病院のソーシャルワーカーに相談するのもおすすめです。
介護保険・医療保険でまかなえないときは
介護・医療保険サービスは充実していますが、かゆいところに手が届かないことがあります。
そこで、ご利用いただきたいのが、保険外サービスです。
コハルの保険外看護サービスでできること
| 介護・医療保険内看護 | コハルの保険外サービス | |
| 場所 | 自宅、自宅周辺と限定的 | 制限なし。全国、全世界可能 |
| 時間 | 20分~90分まで 週に数回(介護度、医療保険か介護保険によって異なる) | 制限なし。 24時間365日対応可能 |
| その他 | 送迎サービスや看護以外のサービス | 送迎サービス・掃除、買い物などご要望に応じて何でも可能 |
このように制限なく、様々なサービスをご利用いただけます。
まずは、保険内サービスでお困りごとが解決できないかという視点で考えることが大切です。
そして、それでも制限の面、例えば夜間の見守りが必要、外出や外泊、受診の付き添いが必要となりましたら、遠慮なく相談ください
ケアマネジャーの資格を有するコハルが、あなたとご家族のお困りごとが解決できるよう、一生懸命お答えさせていただきたいと思います。
問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせくださいませ