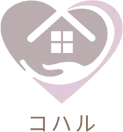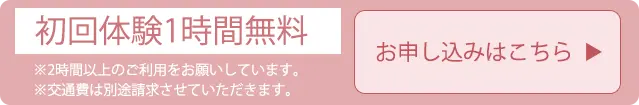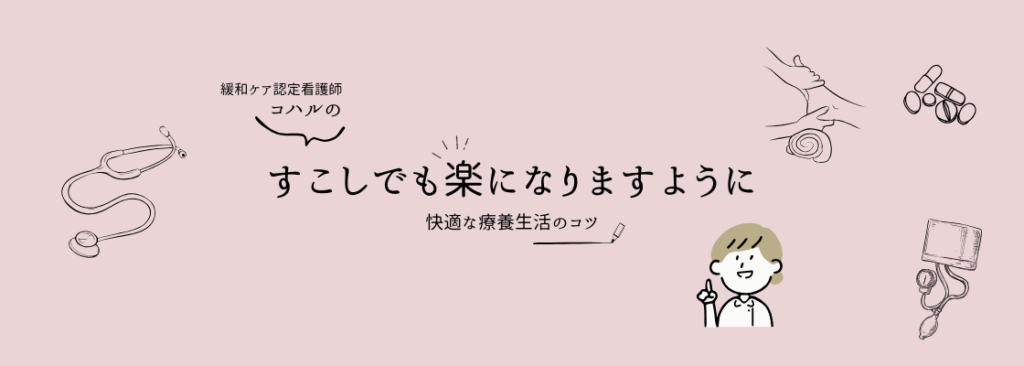
こんにちは
プライベートナーシングコハルの「すこしでも楽になりますように」をご覧いただきありがとうございます。
今回はがんの痛みを和らげるためにできること というテーマでお伝えしていきたいと思います。
がんと闘っておられる方の20~50%の方が、診断時から痛みを感じているといわれています。
痛みがあると日常生活がままならないばかりか、「また痛くなるんじゃないか」「もっと痛みが強くなるんじゃないか」
という不安や心配の種にもなり治療に対する意欲がさがってしまう方もおられます。
また、そんな姿をみてご家族も同じように不安を抱えたり、どうすればいいかわからないという気持ちになることが多くあります。
痛みは、ご自身にしかわからないものです。
我慢してしまったり、医師にお任せとなってしまうと痛みの治療もうまくいきません。
今回はご自身でできる痛みの治療についてお話ししていきたいと思います。
どうして痛みが起こるのか
痛みとは、実質的・潜在的な組織損傷に結び付く、あるいはそのような損傷を表す言葉を使って述べられる不快な感覚体験および感情体験であり、常に主観的なものである
国際疼痛学会
この定義からもわかるように痛みはご本人にしかわからないものです。
人によって同じ刺激や損傷でも平気な方もいれば、そうでない方もおられます。
けれど、それは我慢が足りないわけでもなく、弱虫なわけでもなく、「痛い」という真実だけなのです。
すこし痛みのメカニズムについてお話ししておきます。
痛みは内臓や骨、筋肉、神経が刺激や損傷、炎症をうけることで、脳の感覚を感じるところに伝達され、「痛み」として感じます。
損傷された場所によって痛みの伝達経路が違ったりもします。そして、痛みの感じ方も変わってきます。
その伝達経路によって効果のある薬がたくさん販売されています。
そのため、ご自身の痛みの感じ方はしっかりと詳細に伝えることで早く痛みを和らげることにつながっていくのです。
痛みを和らげるためには
痛みがあることを否定しない
「痛みは本人にしかわからないもの」
「同じ刺激や損傷でも痛みの感じ方は違う、我慢が足りていないわけでもなく、弱虫なわけでもなく「痛い」という真実だけ」
と先述しました。
痛みがあることを「そんなはずはない」「これくらいの痛みなんて平気」と目を背けてしまう方がおられます。
そうすると脊髄や脳から交感神経やアドレナリンが放出され、血管が収縮し、痛みが強くなるという悪循環が完成してしまいます。
神経の痛みは早くに対処しないと痛みが完成してしまう場合もあります。
ぜひご自身の症状を否定せずにいたわり、対処するようになさってください。
また、ご家族の方も痛みがあることをわかろうとすることが大切です。
あまり聞きすぎることも負担になることがありますが、時折気にかけてあげると、心理的ないたみも和らぐことがあります。
痛みについて考えてみる
痛みについて考える
と言っても、ずっとそのことばかり考える。ということではありません。
たくさんやらなければならないことがあるとき
タスクを書いてみると、別のことに集中できるというようになったということはよくあります。
1日1回だけ、痛みについて考え、記録をとることは、他の楽しいこと、やらなければならないことに集中するために有効です。
ひとつの手段として、「痛み日記」や「痛み日誌」が製薬会社や病院などで作成されています。
一度、病院でお聞きになったり、インターネットで調べてみてください。
以下に示すのは、記録事項です。
どうしてそれを記録する必要があるのかという観点から書いていますので参考にしてみてください。
痛む場所はどこ?
痛みの部位を記録することは、原因究明と対処法の選択に役立ちます。
例えば、「ここ!」と明確に示せる場合と、「だいたいここら辺かな・・・」と不明瞭の場合があります。
一般的には明瞭な痛みの場合は、皮膚や骨、筋肉、骨格の痛みの場合が多いです。
不明瞭な痛みの場合は、内臓の痛みであることが多いです。
このように痛む場所によって予測がつきます。
痛みの強さはどれくらい?
痛みの強さは、10段階の数字で伝えると伝わりやすいです。
0が、全く痛みのない状態、10が我慢できない痛みの10段階で評価し、その経過をみていきます。
痛みはご自身にしかわからないことです。ここでも痛みはご自身の感覚でかまいません。
「せっかく薬をくれたのだから」と気を遣って少な目に報告する方もおられます。
決して遠慮せずに、次の一手を決める大切な指標になりますので、しっかり記録してください。
どんな風に痛む?
痛みの性質も原因究明の大きなヒントになります。
例えば、神経の痛みは「ビリビリ」「じんじん」人によっては「水が流れていくような感覚」と言う方もおられます。
内臓の痛みは「絞られるような」「押されるような」と表現される方が多いです。
そして、皮膚や骨格、骨の痛みは「ずきずき」と表現されることが多くあります。
このように原因によって痛み方は変わってきます。
どれくらいの時間痛む?痛む時間はいつ?
痛みの一日の変化を知ることで、日常生活の工夫を考えたり、お薬の調整をすることができます。
こんな方がおられました。腰からくる神経痛があり、朝方に痛みが強く、朝食をとることもままなりませんでした。
腰に負担がかからないように膝の下にクッションをいれたり、朝目覚めてすぐに鎮痛薬をのんだりといった工夫をすると朝食をとることができるようになりました。
このようにいつ、どれくらい痛むのかを知ることで、対処方法が変わってきます。
どんな時に痛む?どんな時に和らぐ?
例えば、お風呂に入っているとき、大好きな趣味をしているとき、人と話しているときなど、どんな時に和らぐのかを注意深く考えてみます。それを記録しておくと、次に痛くなりそうなときに対処する方法が増えます。
反対にこの体勢をしたら痛む、冷えたら痛む、便秘になったら痛む、などどんな時に痛みが強くなるのか。その法則をしっておくとそれを避けることができます。
こちらもご自身やずっとそばにいる家族にしかわからないことですので、ぜひ記録してみてください
痛み止めは効いている?
今まで使用したお薬、今使っているお薬が効いているかどうかを記録します。そして、それがどれくらいの時間がかかった後に効いたのか、それとも効かなかったのか。効いた場合は、どれくらい持続したか。
前述した、数字で表すとさらに有効です。
痛みへの対処方法
ここまで本当におつかれさまでした。
痛みについて考えることは大変なことです。「もうどうでもいいや」という気持ちになってしまう方もおられたと思います。
お辛い場合は、無理をせず、専門家の力を借りて一つずつ紐解いていくことも可能です。
かかりつけのお医者様や看護師さんにご相談いただくか、難しい場合は、わたくしに相談していただいても大丈夫です。
それでは、次にご家庭でできる対処方法についてお伝えします。
痛みの場所

一般的にはここ!と示すことができる場合は、骨や筋肉の痛みであることが多いです。
筋肉の痛みである場合、単にコリだったりすることもあります。
ご自身やご家族に触ってもらってコリコリとした凝りがあり、「そこ!」と感じるならばそこをもみほぐしたり、30秒押してパッと離す虚血圧迫法を試してみてください。温めたりすることも有効です。
腫れがあったり、赤みがある場合は温めない方がいいのでご注意くださいね。
痛みの特徴

びりびりとした神経痛の場合は、一般的には温めたり、無理のない程度でストレッチをしたりすると和らぐ方が多いといわれています。
神経痛はその場所がわるいのではなく、必ずもとの痛みをつくる原因があります。
その部分に負担がかからないような体勢をとるだけで痛みが和らぐ場合もあります。
また、お腹に腫瘍がある方は、「ここ!」と言えない不明瞭な場所に絞られるような、押されるような痛みがあることが多いです。
その場合は、レンジでチンをするタイプのカイロや、タオルをレンジでチンして温罨法をしてみてください。
じんわりと温めることで症状が軽くなる場合があります。
医療の現場でも大好評の対処法です。
くれぐれもやけどにはご注意くださいね。
医師や看護師に伝える
あなたがいろいろ試してみたこと、考えてみたこと、記録してきたことをぜひ医師や看護師に伝えてください。
これだけの情報があれば、痛みの治療は行いやすくなります。
あとは、専門的な画像診断や採血で痛みのアセスメントを行い、それにあったお薬を処方してくれ、あなたにあった飲み方を提案してくれます。
「忙しいのに迷惑かな?」「お任せって言った方がいいんじゃないか」
などと思わずに痛みの治療の中心にいる気持ちで、伝えてみてくださいね。
まとめ
いかがでしたでしょうか
痛みはご自身にしかわからないものです。
私たちは、あなたの痛みを信じています。
痛みが和らぎ、毎日を少しでも快適に過ごすことができるようお祈りしています。
プライベートナーシングコハルのご案内
当社の「心晴れる看護」は、がんと闘う方とそのご家族に寄り添い、専門的なケアと生活サポートを提供しています。
緩和ケア認定看護師の資格をもつ経験豊富な看護師が、保険内サービスで補うことができない部分である夜間や休日、外出外泊時の痛みの管理から、日常生活のお手伝いや見守りまで、幅広いニーズに対応いたします。
主なサービス内容
- 痛みの観察と管理のサポート
- 服薬管理のお手伝い
- 日常生活の介助(入浴、食事、排泄など)
- 家事代行(掃除、片付け、洗濯、買い物など)
- 通院の付き添い
- 帰省、冠婚葬祭、お出かけ、会食などのお付き添い
あなた様の状態や希望に合わせて、柔軟にサービスをカスタマイズいたします。
詳しくは、当社ウェブサイトまたは公式LINE、お電話にてお問い合わせください。がんと闘うあなた様の生活の質の向上をサポートし、少しでも快適な療養生活を送っていただけるよう、心を込めてサービスを提供いたします。